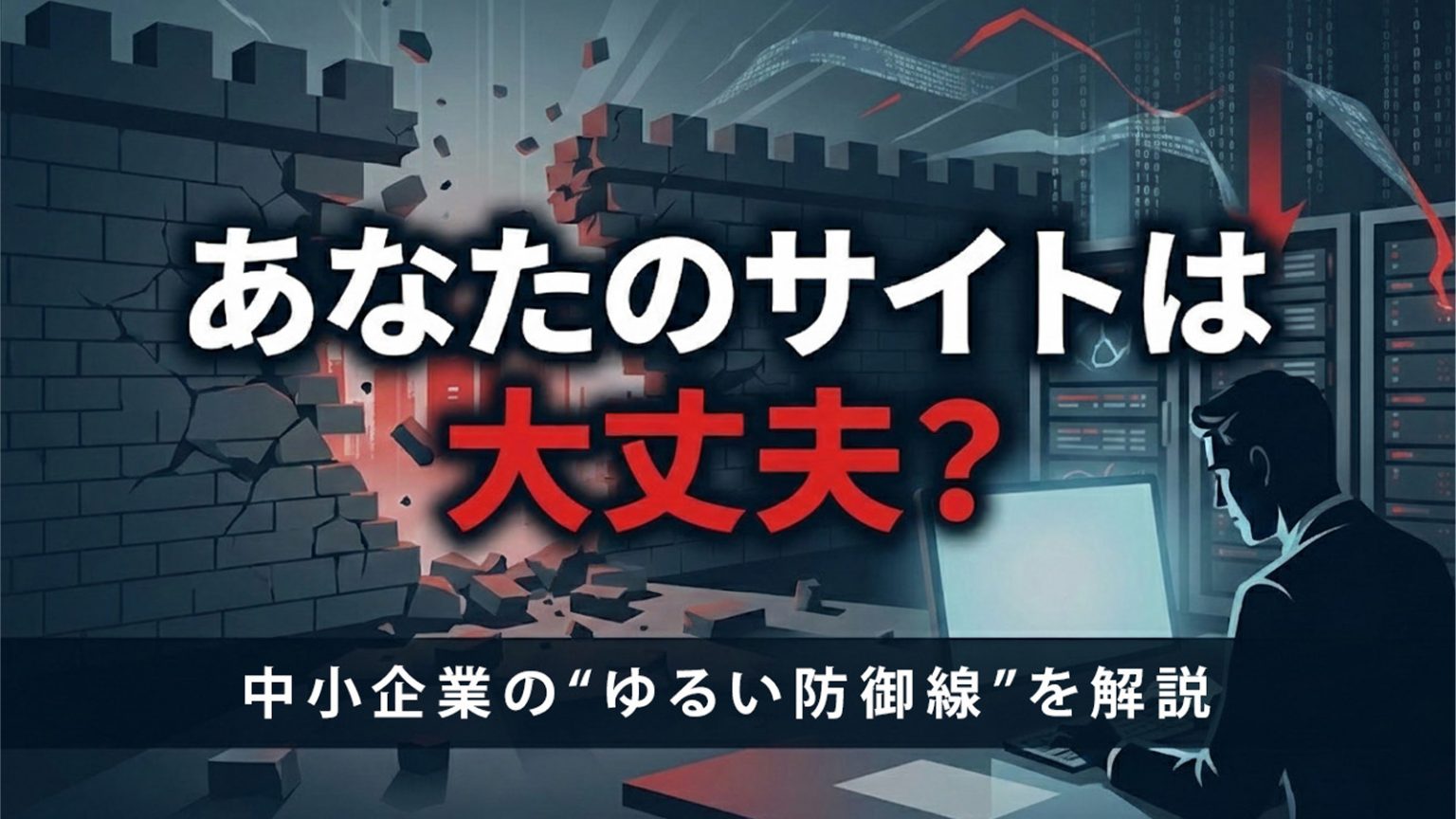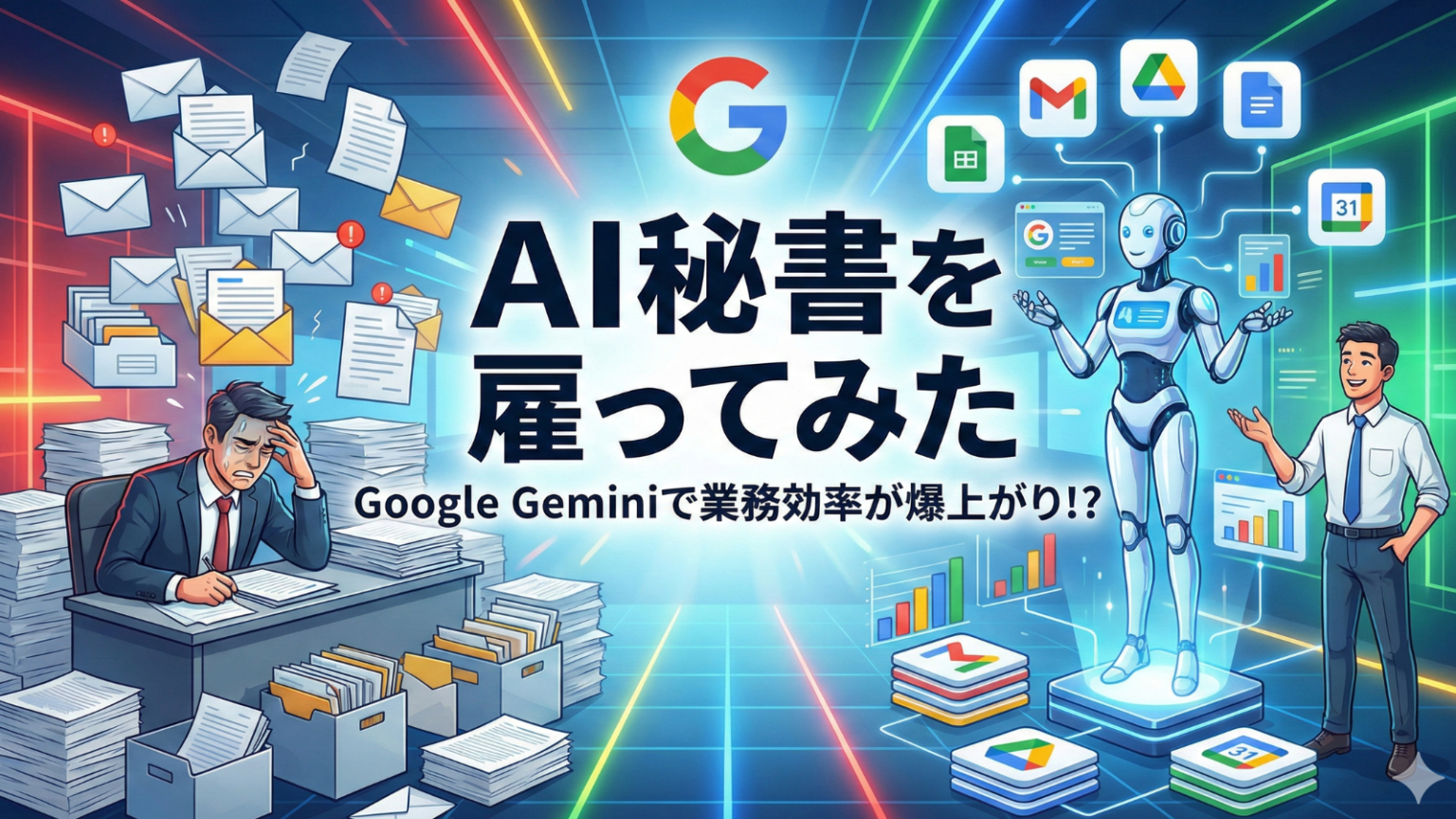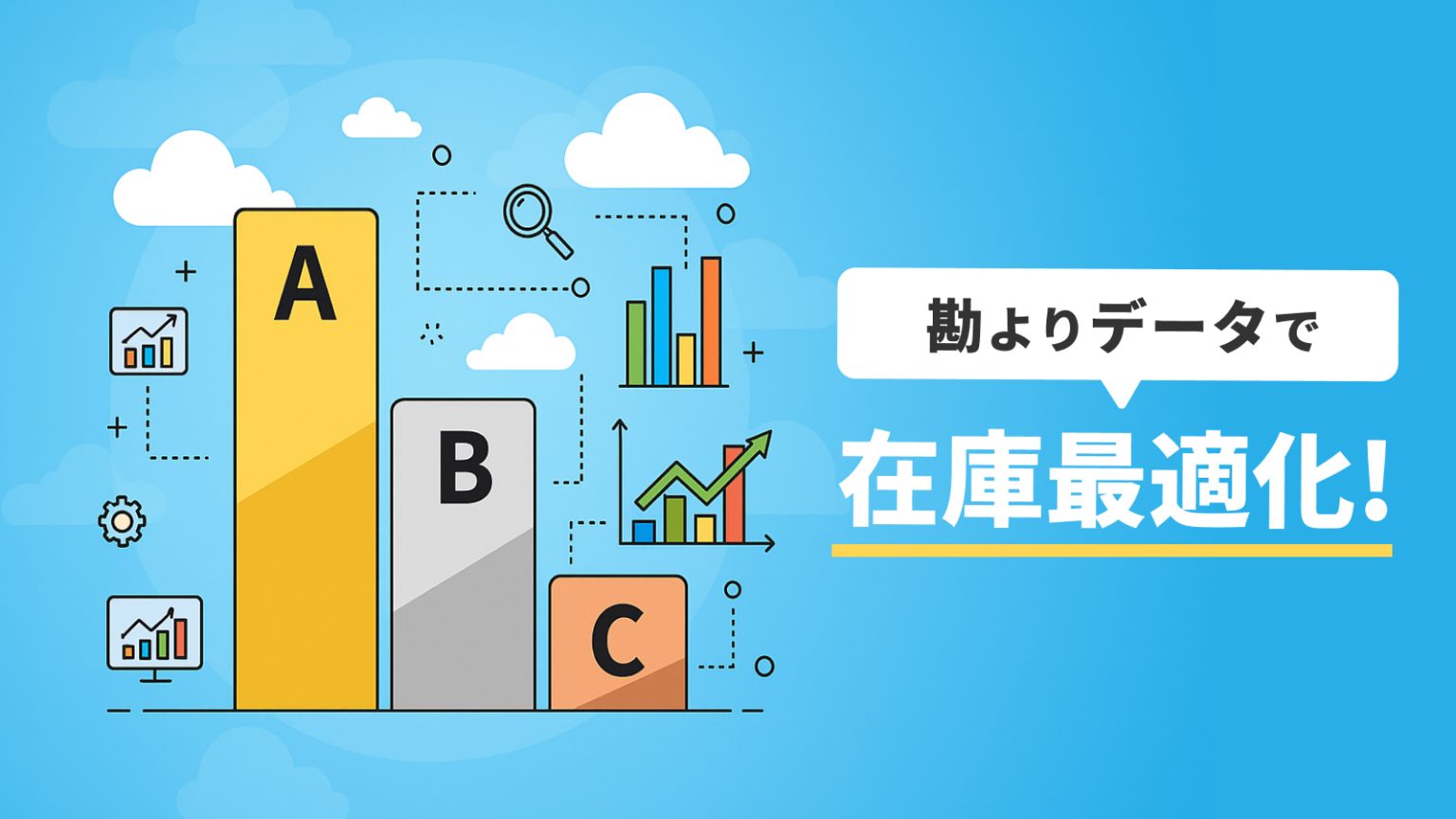ヒロシ
ヒロシカチョー、またハンコのために出社ッスか?これって何とかならないんですかね?



うーん、昔からの慣習だからな…。でも、政府も『脱ハンコ』って言ってるし、何とかしたいとは思ってるんだが…
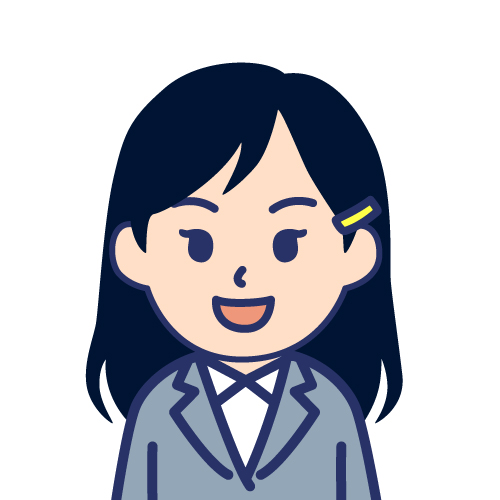
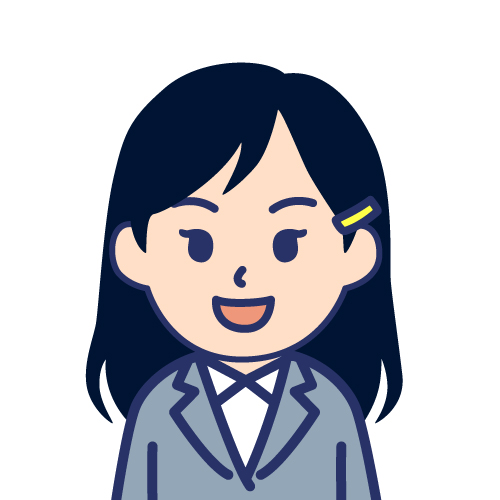
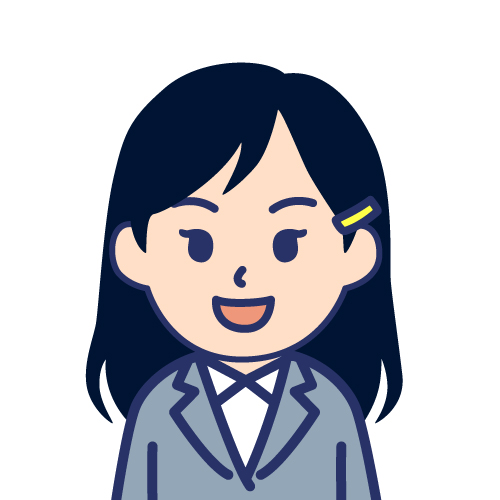
そもそも、どうしてハンコって必要なんですか?
これまで日本では、契約書への押印で本人の同意を示したり、社内の決裁印で承認の意思を示したりと、ハンコはビジネスの様々な場面で重要な役割を担ってきました。しかし、2020年以降、テレワークの普及などを背景に政府も「書面主義、押印原則、対面主義」の見直しを進めています。河野太郎大臣(当時)が全省庁に原則ハンコを使わないよう要請したことも話題になりました。ここでは、中小企業が「脱ハンコ」に取り組むためのポイントについて紹介します。
中小企業が抱える「押印文化」の3つの問題点
今や「脱ハンコ」は、一部の先進的な企業だけの話ではありません。中小企業にとっても、避けては通れない経営課題となっているのです。その理由は、従来の「押印文化」が抱える3つの問題点にあります。
1.テレワークの阻害要因になる
「書類にハンコを押すためだけに出社する」という状況は、社会問題としても取り沙汰されるようになりました。これは単に非効率なだけでなく、従業員の多様な働き方を実現する上での大きな障壁となってしまいます。育児や介護といった事情を抱える従業員や、遠隔地に住む優秀な人材が働き続けることを困難にし、結果として企業の競争力低下につながる可能性もあります。
2.ペーパーレス化を阻害する要因になる
押印のためだけに書類を印刷する企業は少なくありません。せっかくデジタルで作成した文書も、最終的に押印が必要となると紙に出力せざるを得ません。その結果、印刷代や紙代、郵送費、さらには大量の書類を保管するためのキャビネットや倉庫スペースといった、様々なコストが発生し続けてしまいます。これでは、業務効率化や生産性向上を目指すDXの取り組みを阻害する大きな要因となってしまいます。
3.セキュリティ上のリスクがある
社内で頻繁に使われる認印は、誰でも簡単に入手できるため、本人の意思証明としては不適切だと言えます。加えて、紙の書類は 改ざんされたり、紛失してしまったりするリスク も常に付きまといます。閲覧権限の管理も難しく、情報漏洩につながる危険性もあります。実際、安価な印鑑が使われる紙の決裁書は、誰がいつ承認したかの記録が曖昧になりがちで、文書偽造の温床になる可能性も指摘されています。
脱ハンコで会社はこう変わる!6つのメリット
「脱ハンコ」を推進すると、企業には多くのメリットがもたらされます。
1.テレワークなど柔軟な働き方が可能になる
書類への押印のためだけに出社する、という非効率な状況を解消できます。場所を選ばずに業務を進められるようになり、従業員の多様な働き方をサポートできるため、人材確保の観点からも重要です。特に、育児や介護などで出社が難しい従業員にとっても働きやすい環境を整備でき、企業の競争力向上につながります。
2.契約や承認のスピードが格段にアップする
従来の紙ベースの契約では、契約書を印刷・製本し、郵送して相手に押印してもらい、返送してもらうという時間と手間がかかっていました。電子契約を導入すれば、契約データを送信して相手が承認するだけで、すぐに契約を完了させることも可能になります。社内の稟議書なども同様で、承認者がどこにいても手続きを進められるため、意思決定の迅速化が期待できます。
3.業務の進捗状況が「見える化」される
紙の書類の場合、「今、あの書類は誰の手元にあるのか」「どこで承認が止まっているのか」といった進捗状況が分かりにくいという問題がありました。書類を電子化し、ワークフローシステムなどを活用すれば、申請から承認までの進捗状況をリアルタイムで簡単に確認できます。これにより、業務のボトルネックを発見しやすくなり、プロセス全体の改善にもつながります。
4.印紙代や郵送費など、さまざまなコストを削減できる
脱ハンコによるペーパーレス化は、大幅なコスト削減につながります。具体的には、書類の印刷代や紙代、郵送費、さらには契約書に貼る印紙代が不要になります。また、紙の書類を保管するためのキャビネットや倉庫といった物理的なスペースも不要になり、オフィスの省スペース化や賃料の削減にも貢献します。
5.書類の改ざん・紛失リスクを低減し、コンプライアンスを強化できる
電子署名が付与された電子書類は、誰がいつ承認したかの記録が残り、改ざんが極めて困難な仕組みになっています。紙の書類のように紛失してしまうリスクもなく、アクセス権限を設定することで、閲覧できる従業員を制限することも可能です。これにより、認印の不正使用などのリスクも低減でき、企業のコンプライアンス強化に直接つながります。
6.書類の管理や検索が簡単になり、業務が効率化する
キャビネットや倉庫から過去の契約書を探し出す作業は、大きな時間的ロスでした。書類を電子化してクラウド上などに保管すれば、契約日や取引先名、キーワードなどで簡単に検索できるようになり、必要な情報をすぐに見つけ出せます。これにより、書類を探すためだけにかかっていた時間を大幅に削減し、より生産的な業務に集中できるようになります
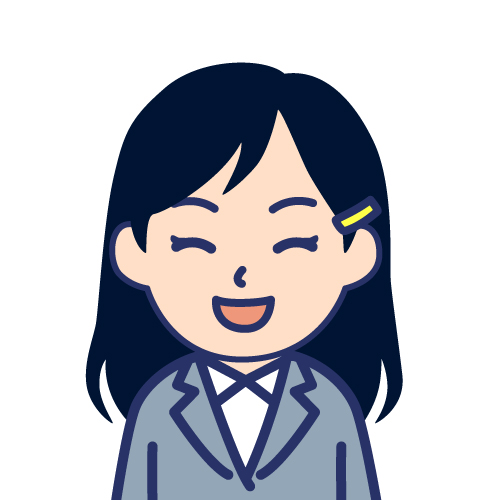
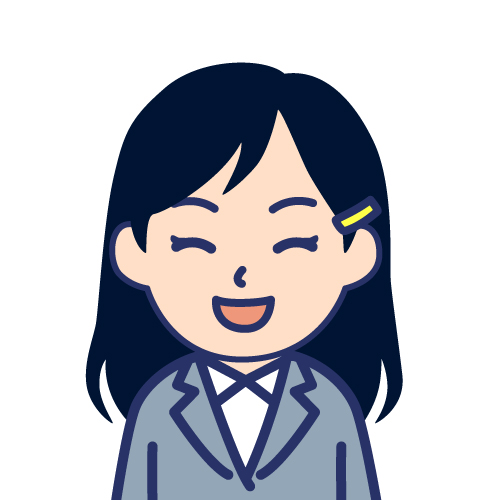
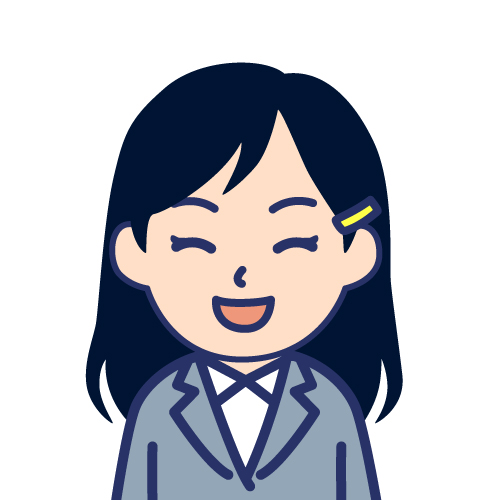
すごい!脱ハンコって、テレワークしやすくなるだけじゃなくて、コスト削減とかセキュリティ強化にもなるんですね。



契約のスピードが上がって、書類がどこにあるかすぐわかるようになるなんて、最高じゃないですか!



ヒロシはよく書類を探すだけで残業しとるからのう。



バレてたのか…
中小企業の「脱ハンコ」実践4ステップ
【ステップ1】対象書類を決める(仕分けする)
まずは、社内にある書類をすべて洗い出し、どの書類から脱ハンコを進めるか優先順位をつけましょう。その際、稟議書や各種申請書といった「社内文書」と、契約書や請求書、見積書などの「社外文書」に分けて考えるとスムーズです。一般的に、社内文書の方が関係者が少なく調整しやすいため、最初のターゲットとしておすすめです。
【ステップ2】目的に合ったITツールを選ぶ
脱ハンコを実現するには、外部のデジタルツール活用が有効です 。ステップ1で仕分けた書類の種類に応じて、最適なツールを選びましょう。
・社外文書向け:電子契約システム、Web請求書発行システム 契約書や請求書、見積書などを電子ファイルで作成し、インターネット上で送付・締結できるようにします。印紙代や郵送費の削減に直結します。
・社内文書向け:ワークフローシステム 稟議書や各種申請などを電子化し、システム上で回覧・承認できるようにするツールです 。誰がいつ承認したかの記録が残り、業務の進捗状況も可視化されます。
どのツールを選べば良いか分からない場合は、無理に自社だけで判断せず、専門家への相談も検討しましょう 。
【ステップ3】社内ルールを見直す
ツールの導入に合わせて、社内の業務フローや関連規程の変更も必要になります 。例えば、就業規則や経理規程などで「契約書は押印のうえ保管する」「経費精算は紙の領収書を添付する」といったルールがある場合、電子署名や電子データを正式なものとして認めるように規程を変更する必要があります 。この見直しを怠ると、せっかくツールを導入しても現場が活用できないという事態に陥りかねません。
【ステップ4】社内・社外へしっかり周知する
新しい業務フローをスムーズに定着させるため、社内への周知を徹底しましょう。ツールの使い方をまとめたマニュアルを用意したり、従業員向けの説明会を開いたりすることで、導入時の混乱を最小限に抑えられます。また、電子契約などに切り替える際は、取引先への事前の説明が不可欠です。自社の取り組みについて丁寧に説明し、理解と協力を求めることが、円滑な移行の鍵となります 。


脱ハンコを阻む2つの壁
社内の壁
脱ハンコを進める上で、まず直面するのが社内の抵抗です。新しいツールの導入には当然コストがかかりますし、それ以上に「これまでずっとこのやり方でやってきた」「新しいツールの使い方を覚えるのが面倒だ」といった、ハンコ文化に慣れ親しんだ社員からの心理的な抵抗感を示される可能性があります。特に、長年アナログな業務に慣れている従業員にとっては、変化に対する不安が大きいものです。
しかし、脱ハンコによって得られるコスト削減、業務効率化、多様な働き方の実現といったメリットが、導入時の初期コストや一時的な学習の労力を上回るケースがほとんどです。経営層がリーダーシップを発揮し、これらのメリットを粘り強く説明することが重要です。単に「新しいツールを導入する」と伝えるだけでなく、説明会を開いたり、マニュアルを整備したりして、従業員一人ひとりの不安に寄り添い、会社全体の取り組みとして理解を得ていく必要があります。
社外の壁
自社が脱ハンコの方針を固めても、契約書や請求書といった社外文書の電子化には、取引先や顧客の協力が不可欠です。相手方の企業文化や業務フローによっては、依然として紙の契約書や押印を必須としている場合も少なくありません。特に、業界の慣習や特定の企業との力関係によっては、電子化への協力を得にくいケースも想定されます。
そのため、一方的に電子化を押し付けるのではなく、電子契約などに移行する際は、あらかじめ取引先に意向を確認し、丁寧な説明を通じて了解を得ておくことが大切です。例えば、「コスト削減や迅速な契約締結といったメリットは、貴社にとっても有益です」といった形で、相手側の利点も伝えながら交渉を進めるとよいでしょう。場合によっては、一部の取引先とは従来の紙ベースでのやり方を併用するなど、柔軟な対応も必要になります。
【まとめ】脱ハンコはDXの第一歩
「脱ハンコ」は、単にハンコを無くすことだけが目的ではありません。それは、デジタル技術を活用して業務プロセスや組織のあり方そのものを見直す「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の第一歩なのです。DXを進められない企業は、今後、優秀な人材の確保が難しくなるかもしれません。ある調査では、在宅勤務の有無が就職先の選択に影響すると答えた若者が半数を超えています。
会社の未来のためにも、まずは「脱ハンコ」という身近なテーマから、会社の改革を始めてみてはいかがでしょうか。
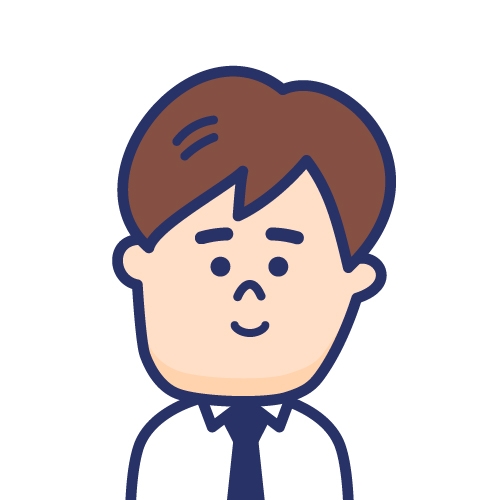
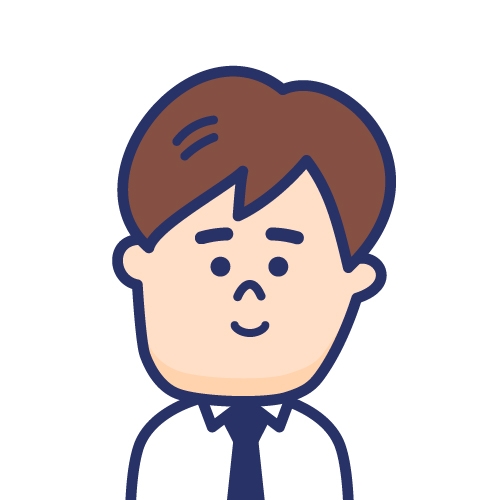
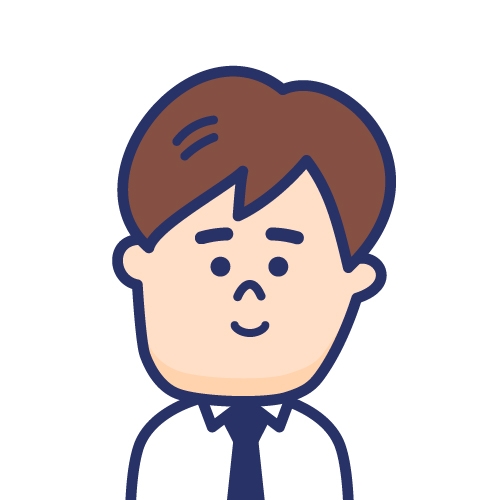
脱ハンコがDXの第一歩かぁ… 。なんだか壮大な話になってきたッスね!
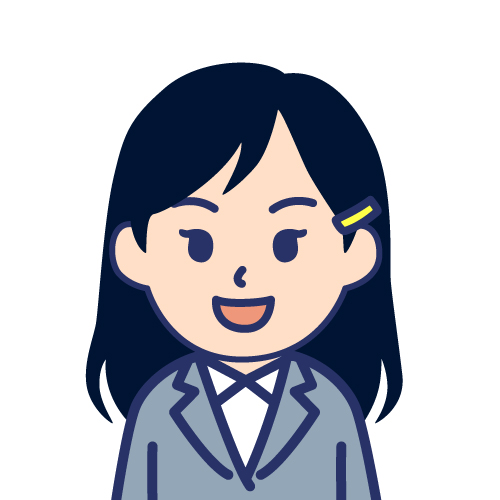
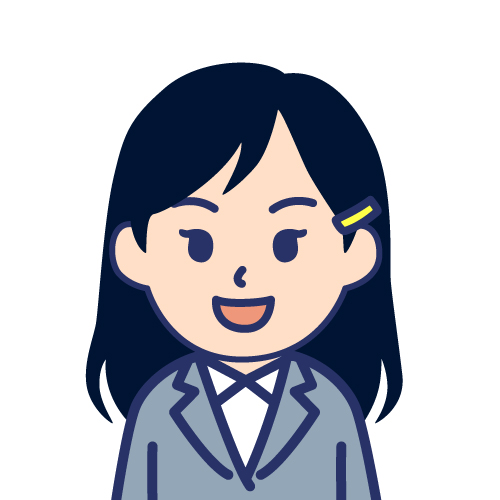
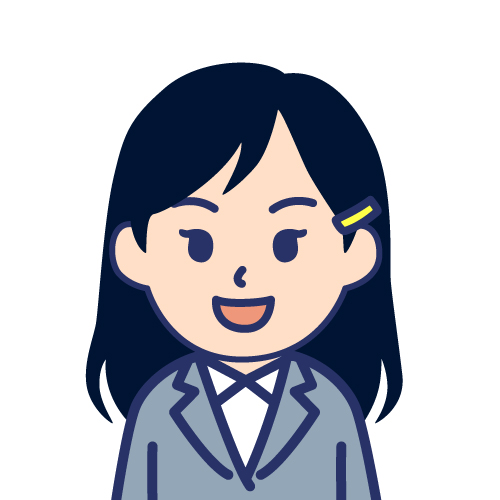
でも、在宅勤務できるかどうかで会社を選ぶ人も多いみたいですし 、これからの会社には必要なことなんですね!



そうだな、優秀な新人にはどんどん入ってきてほしいからな。ヒロシ、うかうかしてられないぞ!



脱ハンコの前に脱ヒロシは困ります~