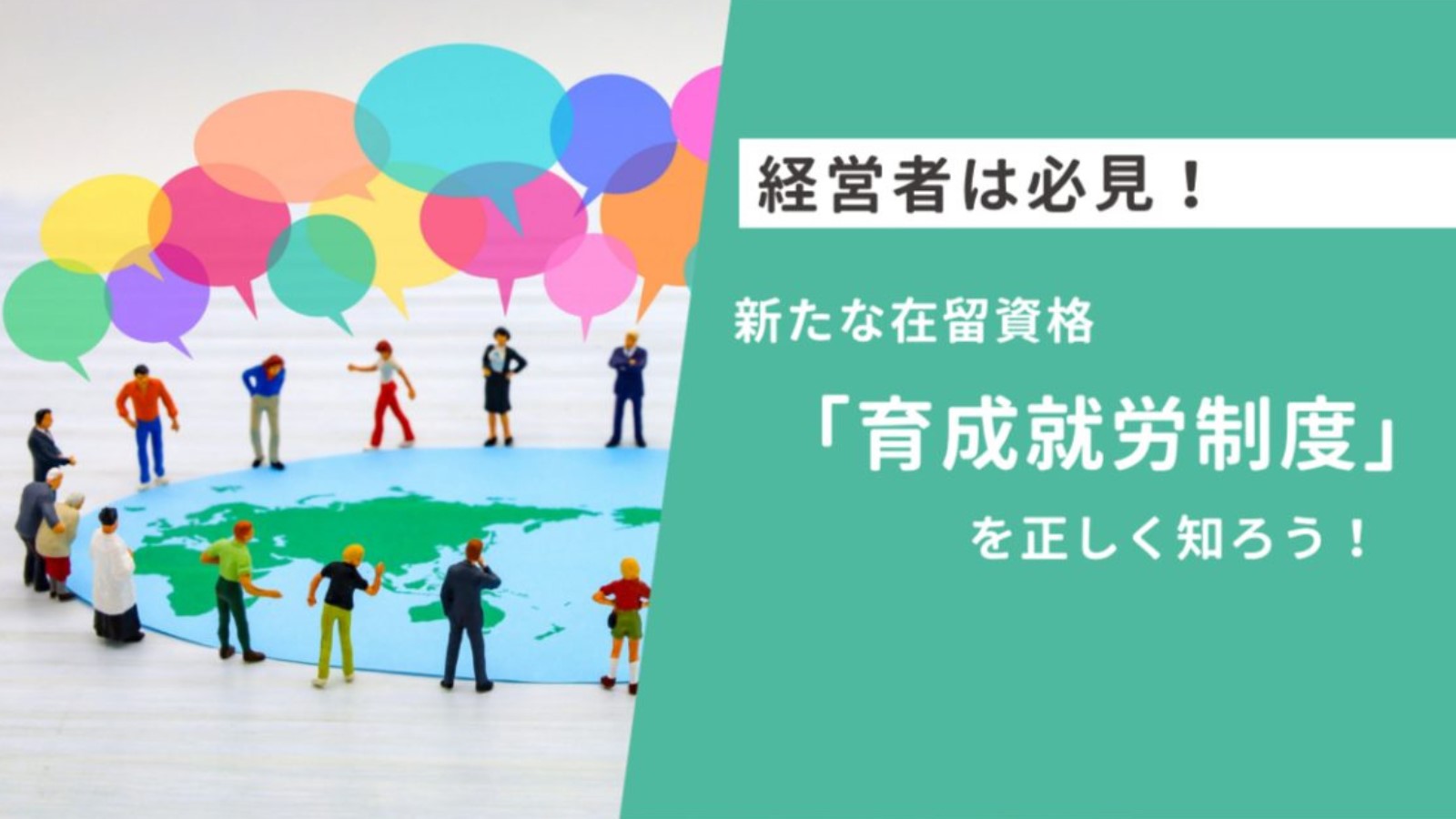カチョー
カチョーシャチョー!今、時代はウェルビーイング経営です!是非わが社でもウェルビーイング経営を導入してください!



おお!なんか横文字でカッコいいな!わかった、検討してみるよ。で、ウェルビーイング経営ってなんだっけ?わかるように説明してくれないかな?



実は私も詳しい内容は知らないんですよ。「健康経営」という言葉もよく聞きますが、同じようなものでしょうか?



オイオイ…
ウェルビーイング経営とは?
近年、企業経営のあり方のひとつとして、「ウェルビーイング経営」が注目されるようになってきました。「ウェルビーイング(Well-being)」という言葉は、「身体面、精神面、社会面において良好であること」を意味し、心身ともに満たされた状態を表現する言葉として認識されています。もともと、世界保健機関(WHO)が“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”
(健康とは、単に病気や虚弱でないということではなく、身体的・精神的・社会的に完全な良好状態である。)と定義づけたことに由来すると考えられています。
これを企業経営に応用したものが「ウェルビーイング経営」です。従業員が健全な環境で仕事ができることを実感し、自身の幸福度を高めることを通じて、会社全体の生産性や持続的成長を実現する経営のあり方です。
似たような概念で「健康経営」がありますが、内容は少し違います。健康経営は主に従業員の心身の健康を通じ、企業の生産性向上を目指すものですが、ウェルビーイング経営は身体・精神に加え、社会での総合的な幸福を追求し、従業員と企業両方の成長を目指したものになります。
なぜ、いまウェルビーイング経営が着目されているのか?
では、なぜいまこの「ウェルビーイング経営」の考え方が着目されているのでしょうか?それは以下のような時代背景が考えられるのではないでしょうか?
1.人材確保の難しさ
日本は急速な少子高齢化に直面しており、労働人口は年々減少しています。特に、中小企業は大企業に比べて給与や福利厚生で優位性を出すことは難しい場合が多く、「人材の確保と定着」が大きな課題です。そして、この状況で重要になるのが「働きやすさ」での差別化です。給与や待遇で勝てなくても、「この会社なら安心して長く働ける」「社員を大切にしてくれる」というイメージを打ち出し、継続して実現することで優秀な人材を引きつけることができます。
2.働き方・価値観の変化
ここ数年で働き方の常識は大きく変化しました。コロナ禍を経てリモートワークやフレックスタイム制が一般化し、社員は「場所や時間に縛られずに成果を出す」ことを重視するようになっています。特に20〜30代の若手世代は、「給料さえ高ければいい」という価値観から、「やりがいのある仕事がしたい」「自分の成長やライフスタイルに合った働き方を選びたい」という価値観へシフトしています。もし会社が古い価値観のまま「長時間労働が当たり前」「社員は会社に合わせるべき」というスタンスを続けていれば、優秀な人材は簡単に離れてしまうでしょう。ウェルビーイング経営は、こうした価値観の変化に対応するうえでも不可欠なのです。
3.SDGs・ESG経営の広がり
「人を大切にする経営」であるかどうかは、今や社会や投資家からの重要な評価軸になっています。
環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視する「ESG投資」では、単に利益を上げるだけでなく、企業がどのように従業員を支え、社会に貢献しているかが問われます。さらに、国連が2015年に採択した「SDGs(持続可能な開発目標)」の中でも、目標8「働きがいも経済成長も」はウェルビーイングの理念と重なります。すべての人が働きがいを持ち、人間らしく生きられる社会を目指すという考え方は、従業員の幸福度を高める経営そのものです。こうした世界的な流れに沿った経営姿勢は、企業ブランドや取引先からの信頼を高めるだけでなく、中小企業が「社会に選ばれる存在」となるための重要な要素です。
働きがいも経済成長も
出典:公益財団法人日本ユニセフ
4.イノベーションの促進や生産性向上
従業員が心身ともに健康で、安心して意見を言い合える職場では、モチベーションや集中力が高まり、生産性が向上します。一方で、ストレスが多い職場では欠勤・離職が増え、業績にも悪影響が出ます。心理的安全性の高い職場づくりは、社員の創造性を引き出し、新しいアイデアや改善提案を生む源泉になるといえるでしょう。つまり、ウェルビーイング経営は「社員の幸福」と「企業の成長」を同時に叶える戦略なのです。


実際にウェルビーイングを実践するためのステップ
次に、ではどのようにすればウェルビーイング経営を実践できるのか、その手順を見ていきたいと思います。ただ一つの手順、といったものはありませんが、以下のような流れを踏むのがわかりやすいのではないでしょうか。
ウェルビーイング経営を実践するためのステップ
- 現状把握:アンケートやヒアリングで従業員の意識や働き方を可視化する。
- 理念・目的の共有:経営者と社員が「自社にとっての幸せとは何か」を話し合い、方向性を明確にする。
- 行動計画の策定:話し合いの結果をもとに、部署・個人単位の目標や行動を具体化する。
- 経営者の支援と承認:現場のアイデアを尊重し、挑戦を後押しする文化を醸成する。
- 取り組みの実践:制度導入や職場改善を小さな一歩から始め、継続的に実行する。
- 定期的な見直し:年数回の振り返りやアンケートを通じて、取り組みの成果を確認・改善する。
実践のためのステップ
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構
例えば、1.現状把握に関してはパーソル総合研究所が無料で提供する「はたらく人の幸せ/不幸せ診断」などのオンライン診断ツールもあります。是非、実際に活用してみてはいかがでしょうか。
「はたらく人の幸せ/不幸せ診断」
出典:パーソル総合研究所



おお!無料で提供しているのか!気軽に試すことができるね!



そうですね!早速わたしもやってみます!
実践事例:株式会社日興テクノス(神奈川県)
ここでは、「ウェルビーイング経営」を実践した中小企業の例を紹介しましょう。
神奈川県が推進する「ウェルビーイング経営モデル事業」に参加した中小企業・株式会社日興テクノスでは、
フレックスタイム制や在宅勤務制度の導入、健康管理制度の強化など、働きやすさと健康を両立する仕組みを整備しました。
特に注目されるのは、従業員の“幸福度”を見える化し、経営判断に反映する仕組みを作った点です。社員アンケートやワークショップを通じて、「自分の働き方を自分でデザインできる職場」を目指したことで、社員の満足度が上昇し、離職率の低下につながりました。
実践事例
出典:株式会社日興テクノスウェルビーイング経営モデル
中小企業経営者がいま、すべきこと
ウェルビーイング経営は、大企業だけの贅沢な取り組みではありません。むしろ社員との距離が近く、現場の声をすぐに反映できる中小企業こそ実践しやすい経営スタイルです。
経営者がまず行うべきことは、難しい制度づくりなどではなく、「社員の幸せを経営の一部として考える」姿勢を明確に打ち出すことにあります。
その第一歩として、次のような行動をおすすめします。
- 経営理念に「人の幸福」を明文化する:経営計画書や社内メッセージに「社員が安心して働き、成長できる会社をつくる」と掲げる。
- 現場の声を聞く時間を増やす:定期的に、社長自ら社員と話す「対話」の場をもうける。
- 小さな改善から始める:たとえば「お昼休憩の時間を確保する」「感謝を伝える場をつくる」など、低コストですぐにできることに着手する。
- 成果を可視化する:離職率、欠勤率、社員満足度などを指標にして、継続的に確認する。
- 学び続ける:他社事例や専門家の情報を取り入れ、自社流の取り組みを磨く。
ウェルビーイング経営は一度きりの施策ではありません。社員が安心して働ける環境を少しずつ整えることが、結果として業績の安定・採用力の強化・企業ブランドの向上につながります。
「人を大切にする会社が、最も強い会社になる。」その第一歩を、今日から始めてみてはいかがでしょうか。



なるほど、社会的な責任だけでなく、これから企業も発展していくために不可欠な考え方なんだな!できることからどんどん取り入れていきたいね!



早速わたしもすぐにできるウェルビーイングの施策を考えました!社員食堂のご飯「おかわり無料サービス」を始めましょう!これで従業員のモチベーションもアップですね!



食べ過ぎて午後の生産性が心配だな…