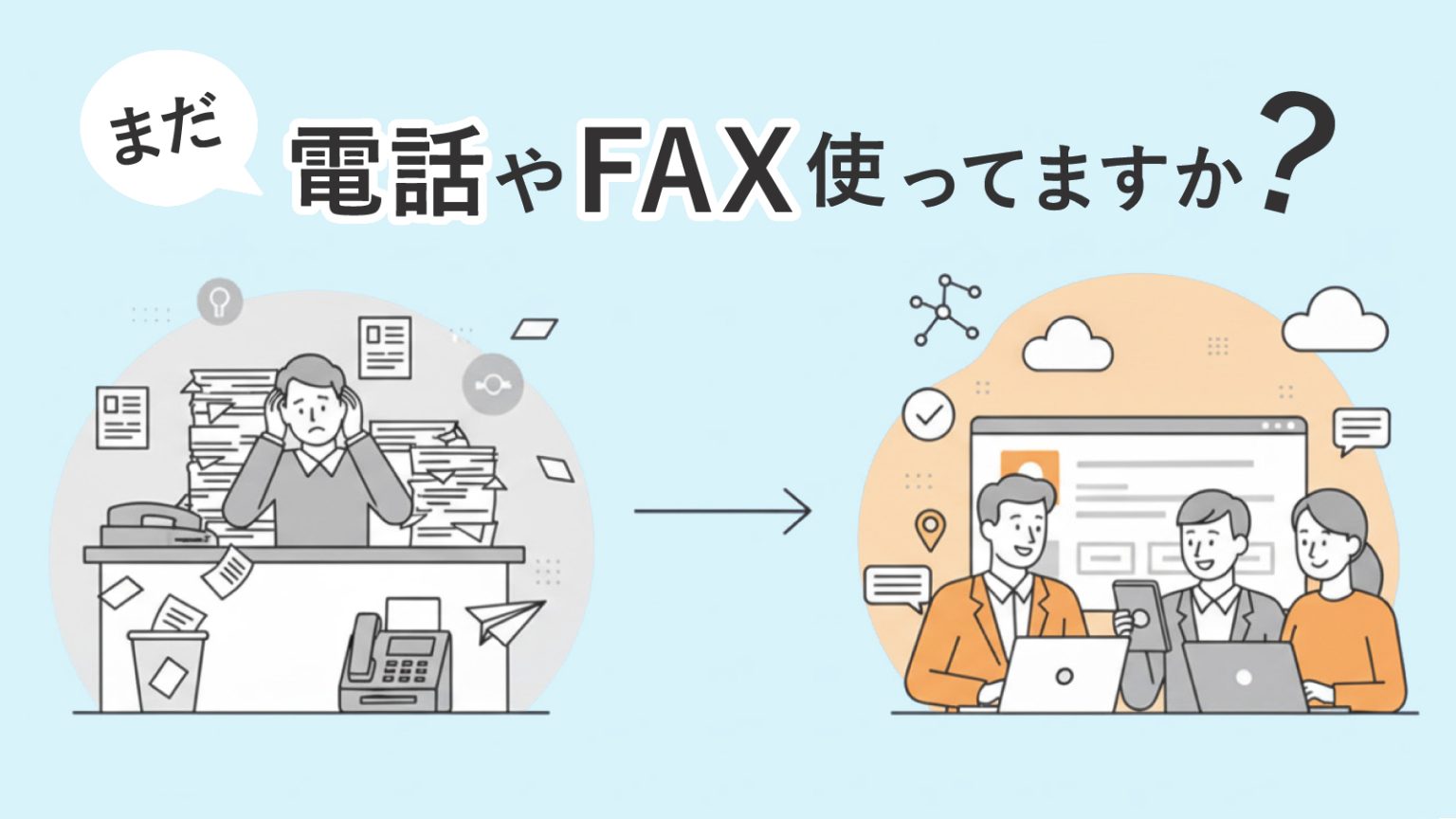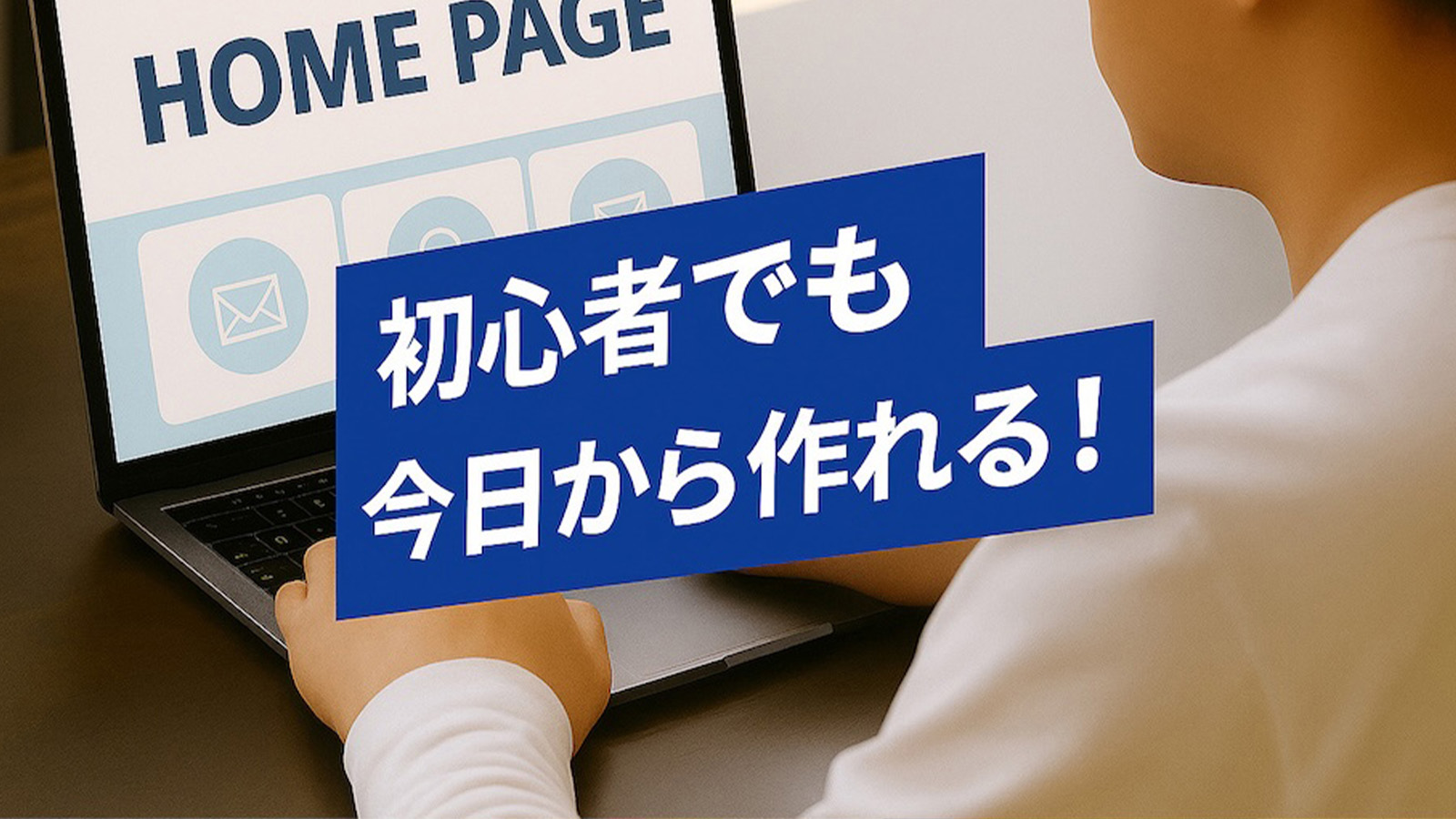サクラ
サクラあ〜もう、ブログネタが全然思いつかないです!毎回“お知らせ”だけじゃ読まれませんよね…?



オレも前に“施工実績しか更新してない”ってカチョーに怒られたっス。



怒ってない。注意しただけだ。それに、最近は“中身より続けること”が大事って聞いたぞ?
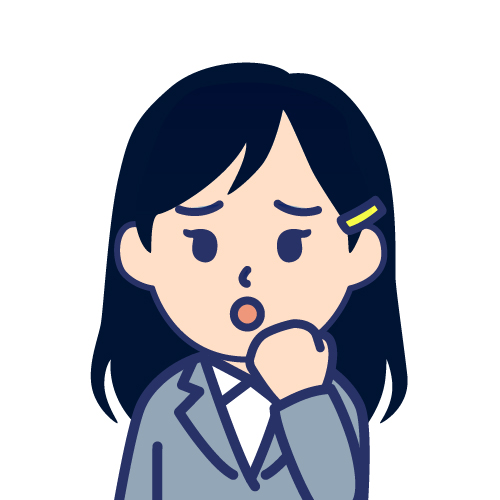
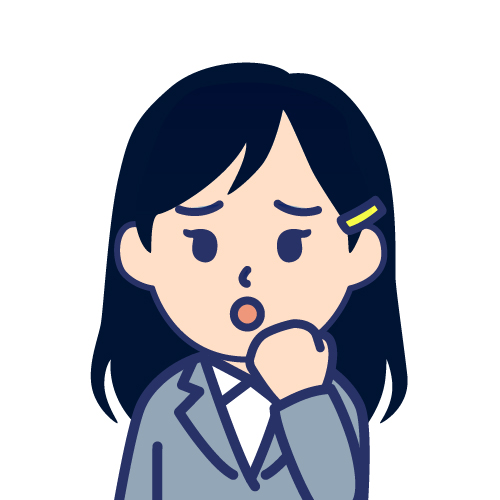
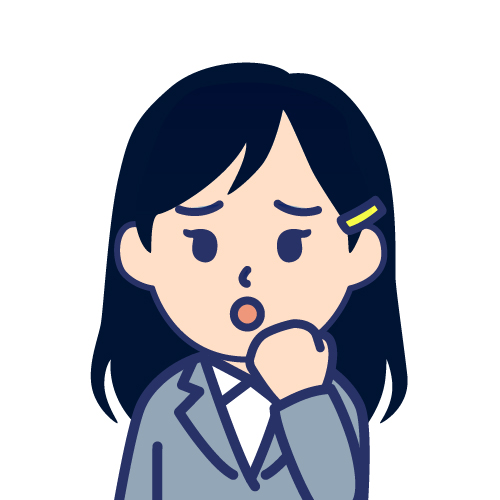
でも、どうやったら続けられるんですか?
「ブログを書かないと…」と思いながらも、気づけば何カ月も更新していない──。多くの企業や店舗がこの悩みに直面しています。しかし、そもそもブログが続かないのは“ネタがない”からではなく、“ネタの見つけ方が間違っている”可能性があります。この記事では、ホームページの集客につながる記事ネタの見つけ方と、続ける仕組みづくりを紹介します。
ブログが続かない理由
多くの企業や担当者が「ブログを更新しなければ」と感じつつも、何回か更新した段階で止まってしまいます。その原因は、やる気の問題ではなく、多くの場合「何のために書くのか」が明確でないことが最大の理由です。「とりあえず情報発信を」と始めたブログは、早い段階でネタ切れを起こします。なぜなら、目的が“会社視点の情報提供”にとどまっているからです。
企業ブログの役割は、「顧客の疑問や不安を解消し、信頼を積み重ねること」にあり、「発信義務」ではなく、「お客様との対話の場」として機能させることが必要です。たとえば、日々のお問い合わせ内容、営業現場での会話、スタッフの工夫など。それらはすべて、読者の関心から生まれた“価値ある情報”です。「頑張ってネタを考える」のではなく、“お客様の声に耳を傾ける習慣”を持つことで、書くべき記事のテーマは自然と見つかります。
集客につながる記事ネタの3つの方向性
企業ブログを集客につなげるには、まず「どんなタイプの記事を書くと成果につながるか」を整理する必要があります。よくない例としては、サービス紹介やキャンペーン告知ばかりのいわゆる“売り込み”の記事ばかり更新してしまうことです。売り込みの記事ばかりでは、読者は「宣伝」としか受け取らず、滞在時間が伸びません。集客につながる記事は、読者の心理や行動の流れを踏まえて設計する必要があります。代表的な切り口が以下の3つです。
1. 「悩み解決型」
読者が検索エンジンで調べるのは、「今の悩みを解決したい」「判断に迷っている」とき。このタイミングで役立つ情報を届けられれば、自然と信頼が生まれます。
たとえば、
- 「ホームページのアクセスを増やすには何をすればいい?」
- 「補助金ってどんな条件で使えるの?」
- 「採用ページはどんな内容を書けば応募が増える?」
悩み解決型の記事は“検索される言葉”と“読者の疑問”を一致させるのがポイントです。
こうした記事は、一度公開すれば長期間アクセスを集め続ける“資産型コンテンツ”になりやすいです。またSEO効果だけでなく、「この会社は詳しい」「信頼できる」という印象づけにもつながります。
2. 「ストーリー型」
「悩み解決型」などの検索流入だけでは、ファン化は進みません。商品やサービスの“裏側”にある人や想いを伝えることで、読者との心理的距離が縮まります。
たとえば、
- 「この商品をつくるきっかけになったお客様の声」
- 「スタッフが語る“仕事のこだわり”」
- 「創業当時の失敗談とそこからの学び」
こうした記事は、直接的な集客には見えなくても、“企業の信念”を伝えるブランディング記事として効果を発揮し、「どんな会社か?」よりも、「どんな人たちが働いているか?」を知る機会になり、ファンは増えていきます。
3. 「比較・体験型」
「悩み解決型」と「ストーリー型」が“認知・興味”のフェーズを担当するなら、「比較・体験型」は“検討・意思決定”のフェーズを担う記事といえます。
たとえば、
- 「AプランとBプランの違いを実際に比べてみた」
- 「他社製品を使ってみて感じた正直な違い」
- 「導入前後でどう変わったか?お客様の声」
こうした記事は、すでに検討フェーズにいる見込み顧客に強く響きます。特にBtoBや高単価商材では、「信頼できる判断材料」が購買の決め手になります。“企業目線の比較”ではなく、“ユーザー視点の比較”として書くのがポイントです。率直な実感を伝えることで、「この会社は誠実だ」と感じてもらえます。



悩み解決型、ストーリー型、比較体験型…これで3パターンっスね!



これならネタに困らなそうだな!でもネタが出ても続かないのが問題なんだよなぁ…



(突然登場)続けるには“仕組み”だよ、カチョー!ブログもDXも“習慣化”が命だ!
ネタを生み出す具体的な方法
多くのブログ担当者がネタ探しに苦労していますが、“書く視点”を少し変えるだけで、簡単にネタは見つかります。ネタが生まれないのは、情報がないからではなく、「それをネタとして認識できていない」だけの可能性が高いです。ここでは、明日から実践できる3つの探し方を紹介します。
1. 社内から探す
まず最初に見直すべきは、普段の“日常”です。社内で当たり前に行っていること、スタッフが自然に工夫していること、お客様対応のちょっとした気配りなど、これらは、社外の人にとっては十分に記事にする価値のあるネタになります。
たとえば:
- 「現場で使っている便利ツールを紹介」
- 「新人研修で伝えている仕事の基本」
- 「社員が語る“うちの会社の好きなところ”」
これらの記事は単なる社内紹介ではなく、企業文化や信頼感を伝えるブランディング要素として機能します。ポイントは、専門知識をやさしく翻訳することです。業界の常識でも、一般の人には十分価値のあるコンテンツです。普段の何気ない日常にもネタはたくさんあります。
2. お客様から探す
もっとも信頼性が高く、読者の共感を得やすいのは、お客様の声に基づいた記事です。問い合わせやレビュー、営業時の質問、SNSでのコメントなど、すべてニーズとして記事にする価値があります。
たとえば:
- 「お客様からよく聞かれる質問に答えます」
- 「実際にサービスを利用した方の体験談」
- 「問い合わせの背景にある“本当の困りごと”を掘り下げる記事」
こうしたお客様の声などは「なぜそれを知りたいのか?」を理解し、読者の課題や不安を深掘りすることで、読者にとってより価値のある記事になります。
3. トレンドから探す
ブログを定期的に更新するには、トレンドを意識した記事も効果的です。いつの時期でも使える“定番テーマ”だけでなく、旬の話題を絡めることで更新のきっかけが生まれ、アクセスの波を作ることができます。
たとえば:
- 「春の新生活シーズンに合わせた住宅のメンテナンス記事」
- 「年末前に確認したい税務・補助金まとめ」
- 「トレンド技術を自社サービスとどう結びつけるか」
こうしたトレンド記事は、検索されるタイミングが限定されるため、短期間でアクセスを集めやすいです。
補足:ネタを見つける“習慣”を作る
一度ネタ探しの視点を身につけると、社内の雑談やお客様との会話の中にも「これ、記事にできるな」という瞬間が出てきます。
たとえば、
- 社内チャットで出た質問を週に一度ストックする
- 会議の雑談やトラブル対応を「学び記事」にする
- 現場写真を撮るついでに記事ネタのメモを残す
「これ、記事にできるな」と思った際に忘れないよう、“気づいたらメモしておく”くらいの軽さで記録する習慣を持つと、更新が続けやすくなります。
続けるための仕組みづくり
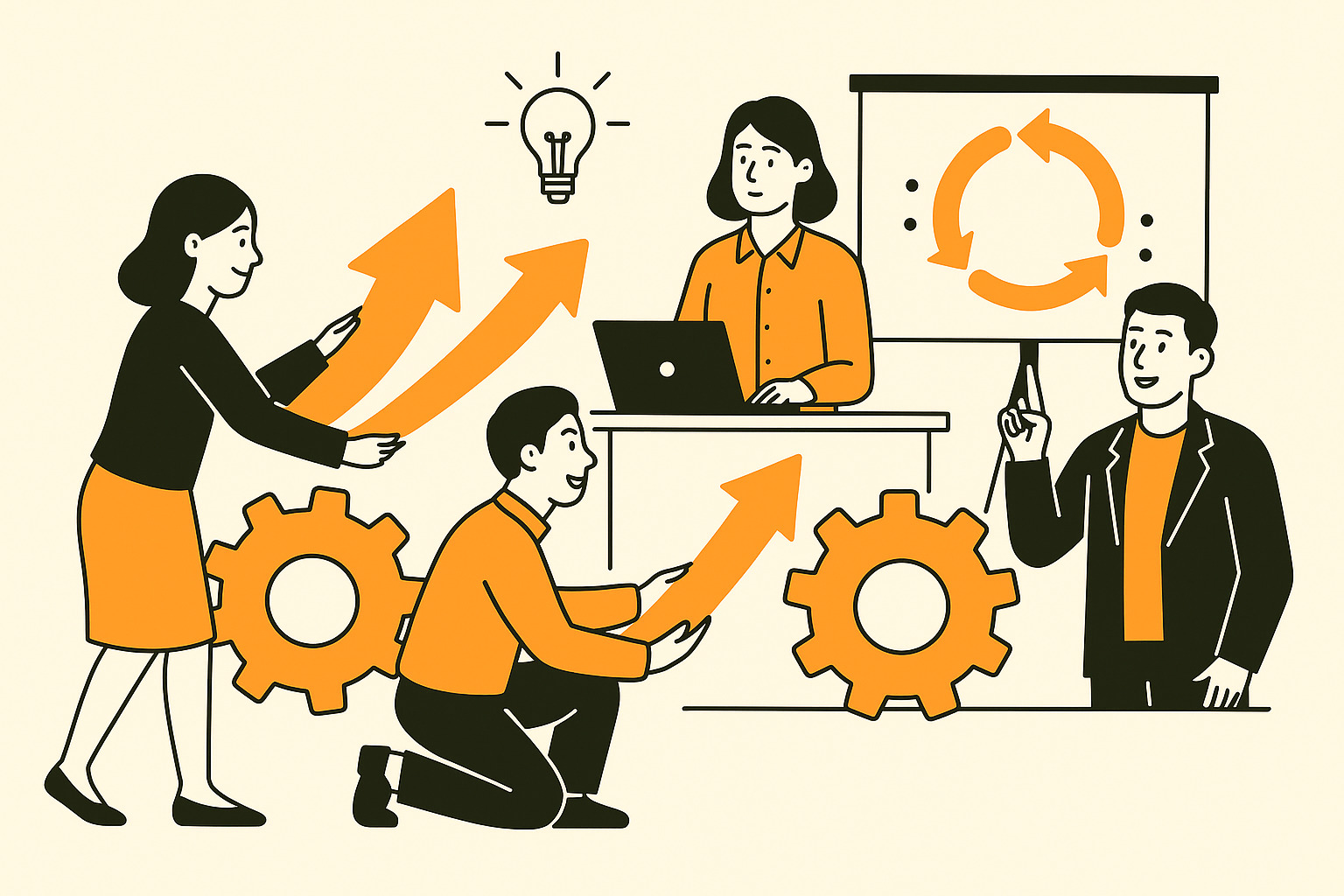
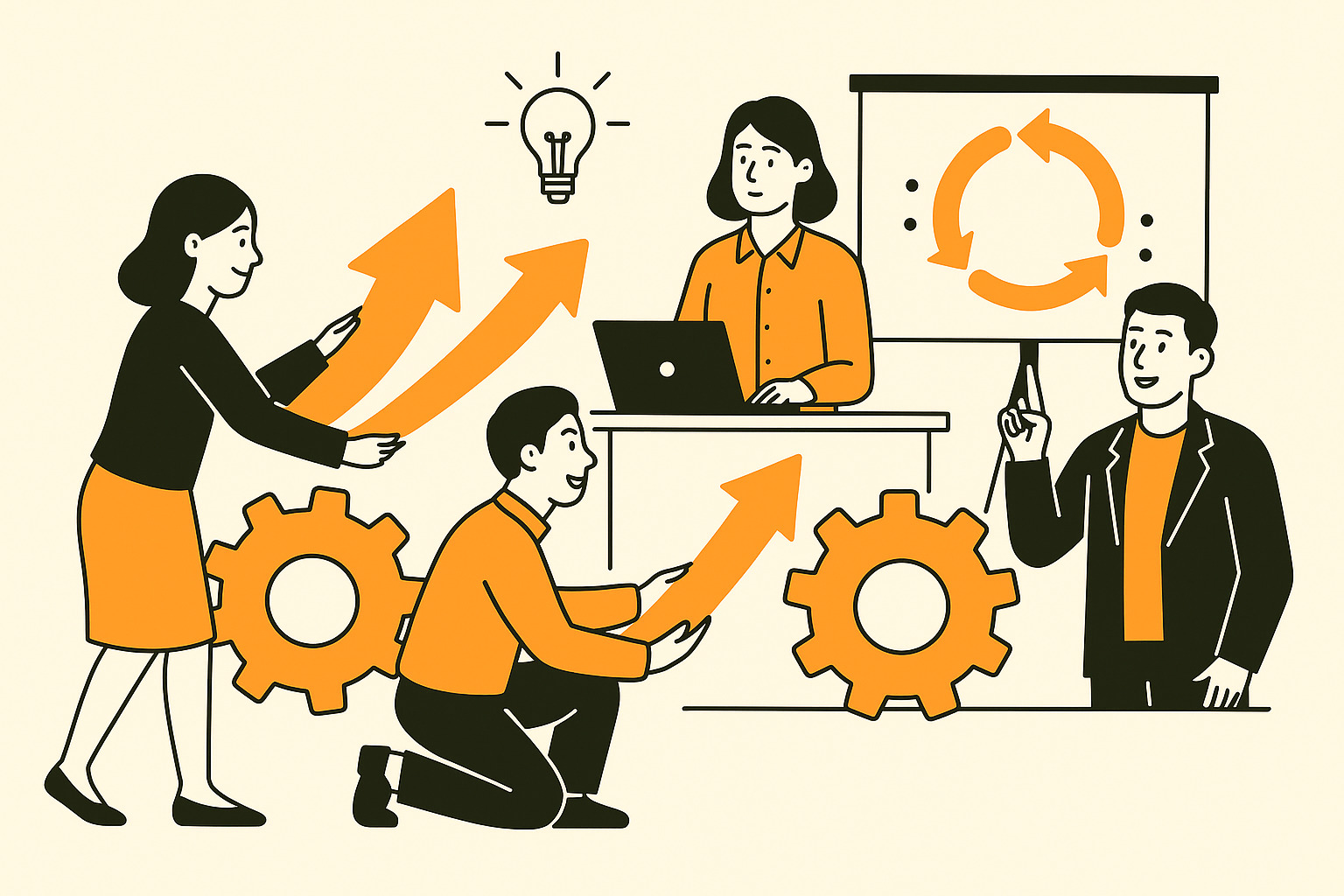
ブログ運用がうまくいく会社と、途中で止まってしまう会社のよくある違いは、“意欲の差”ではなく“仕組みの有無”です。
モチベーションに頼る運用は、途中で挫折してしまう可能性が高く、定期的な更新は難しくなります。一方で、「自然と更新できる流れ」を設計している会社は、無理なく発信を継続できます。ここでは、ブログを“人に依存させない仕組み”に変えるための3つの視点を紹介します。
1. 役割とプロセスを決めて「属人化」を防ぐ
まず最初に整えるべきは、運用フローの明確化です。多くの企業では「書ける人が書く」「時間があるときに更新する」といった属人的な運用になりがちです。これでは、担当者の異動や繁忙期が来るたびに更新が止まってしまいます。理想は、次のように役割分担とスケジュールを明確にすることで継続的な更新がしやすくなります。
| 役割 | 主な業務 | 担当イメージ |
|---|---|---|
| 編集・企画担当 | ネタ出し・テーマ設定・構成案作成 | マーケ/広報担当者 |
| 執筆担当 | 原稿作成・修正・画像選定 | 現場スタッフや外部ライター |
| チェック担当 | 事実確認・表現確認・SEO確認 | 上長・広報責任者 |
| 更新担当 | CMS登録・公開・効果測定 | 制作/管理担当者 |
このように分業化しておくことで、「担当者が変わっても続く」体制が生まれます。さらに、「毎月第2水曜に公開」「1本につき執筆→校正→公開を2週間で完結」など、更新サイクルを固定にしてルール化することで、継続的な記事更新ができるようにします。
2. 負担を減らす仕組みをつくる
継続の最大の敵は「負担感」です。忙しい日常業務の中でブログを書くには、ムリなく続けられる工夫が欠かせません。
いくつかの実践的な方法を紹介します。
- テンプレート化する:
構成をテンプレート化して固定すれば、毎回ゼロから考える必要がなくなります。
タイトル・見出し・まとめ文など、フォーマット化するだけで心理的ハードルが大幅に下がります。 - 定例の“ネタ出し会議”を設ける:
月1回15分でもOK。複数人で話すと、テーマが生まれやすくなります。
「現場で印象に残ったこと」「お客様に褒められた事例」など雑談レベルでも十分効果があります。 - 書かない更新を取り入れる:
写真1枚+短文、または動画の埋め込みでもOK。
“更新の継続”が最も重要で、記事の長さより「発信を止めないこと」が重要です。
こうした工夫により、「やらされるブログ」から「自然に続くブログ」へと変化していきます。
3. 成果を“見える化”してモチベーションを保つ
人は“成長が実感できること”に喜びを感じます。ブログ運用も同じで、「発信がどんな効果を生んでいるか」を可視化することで、チームの意欲は長く続きます。
「この記事から○件の問い合わせが来た」「お客様がブログを読んで来店してくれた」といった成果を共有すれば、「発信には意味がある」という実感を持つことができ、継続への原動力になります。
まとめ ― 続けることが、結果につながる
ブログは「書くこと」が目的ではなく、お客様とつながるための手段です。最初は思うようにアクセスが伸びなかったり、ネタが出てこなかったりするかもしれません。でも、続けていくうちに少しずつ“読まれる記事”が見えてきます。
今回紹介したように、「悩み解決型」「ストーリー型」「比較・体験型」の3つの方向を意識すると、記事のテーマが整理しやすくなります。大切なのは、完璧を目指すことよりも、とにかく止めないことです。お客様の疑問に答えたり、日々の出来事を少し共有するだけでも、それが信頼につながっていきます。焦らず、楽しみながら、自分たちのペースで続けていきましょう。
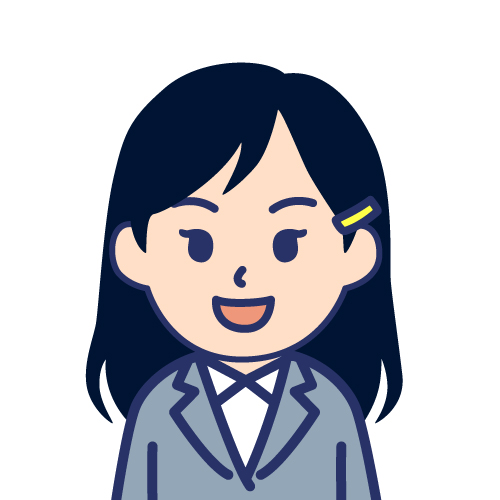
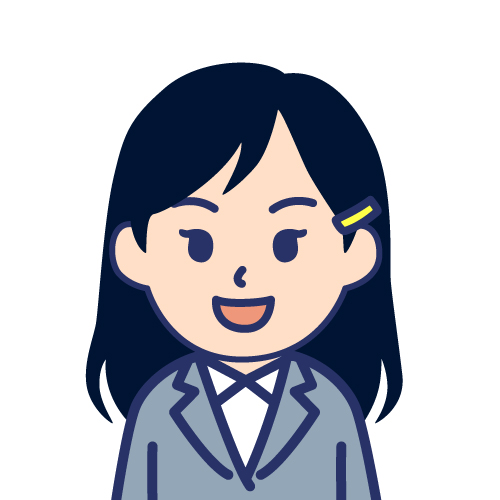
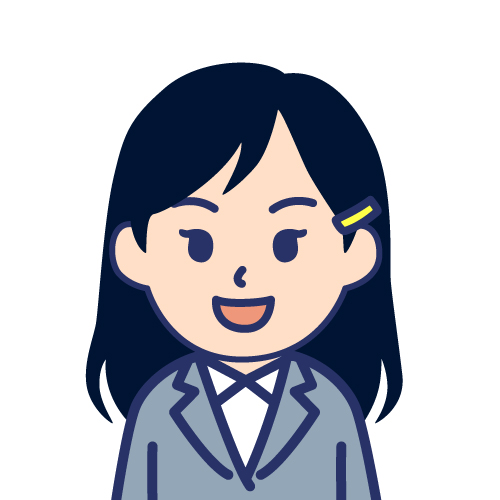
“続ける仕組み”って、難しいと思ってたけど…ちょっとワクワクしてきました!



いい心がけだな。最初のうちは形からでもいい。続けてりゃ、そのうち“流れ”ができる。



うむ。人もブログも、止まらず動いておれば、いつの間にか育つものじゃ。